皆さん、こんにちは。兵庫県神戸市を拠点に、兵庫県南部地域で総合建設業やリフォーム事業を手掛ける橋本建設株式会社です。
昨今、「建設業の若者離れは当たり前だ」という声を、ニュースやインターネットで頻繁に目にするようになりました。建設業への就職や転職を考えたとき、「将来性はあるのか?」「本当に働いていける環境なのか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
建設業は、住宅、学校、病院、道路、橋など、人々の生活と社会の基盤を文字通り「創り上げる」非常に重要な仕事です。しかし、その魅力が若者たちに十分に伝わらず、「きつい」「古い」といったネガティブなイメージばかりが先行している現状があります。
この記事では、そうした不安から目をそらすことなく、まずは建設業界が直面する「若者離れ」という厳しい現実を、データを元に解説します。その上で、なぜ「当たり前」とまで言われてしまうのか、その根本原因を深く掘り下げます。
■データが示す「建設業の若者離れ」という現実

まず、向き合うべき「若者離れ」の現状を、客観的なデータで見ていきます。これは感覚的な話ではなく、数字として明確に表れている危機と言えます。
・ベテランだらけの現場:就業者の年齢構成が示す未来
国土交通省が公表しているデータを見ると、建設業の年齢構成がいかに偏っているかが分かります。
建設業就業者全体のうち、55歳以上のベテラン層が約35%を占めているのに対し、未来を担うべき29歳以下の若年層は、わずか11%〜12%前後に留まっています。これは、全産業の平均と比べても若年層の割合が著しく低い、憂慮すべき状態です。
このままの構成比で推移した場合、今後10年で、現在の現場を支えている経験豊富なベテラン技術者たちが、一斉に定年退職を迎えます。彼らが長年培ってきた貴重な技術やノウハウを、受け継ぐ若者が圧倒的に不足しているのです。
さらに、団塊の世代が一斉に後期高齢者となる「2025年問題」も目前に迫っており、ベテラン層の退職がさらに加速することが予想されます。このままでは、日本の社会インフラを維持・更新していくことさえ困難になりかねない状況となっています。
・入ってもすぐに辞めてしまう…高い早期離職率
問題は、若者が入職しにくいことだけではありません。せっかく希望を持って建設業界に飛び込んだ若者が、短期間で辞めてしまう「早期離職率の高さ」も、人手不足に拍車をかけています。
厚生労働省の調査によると、高校を卒業してすぐに入社した新卒者の場合、3年以内に離職してしまう割合は、全産業の平均よりも高い水準で推移しています。これは、業界全体として、若者を迎え入れ、育て、定着させるための環境整備が追いついていなかったことの証左と言えるでしょう。
■若者離れは「当たり前」と言われる理由
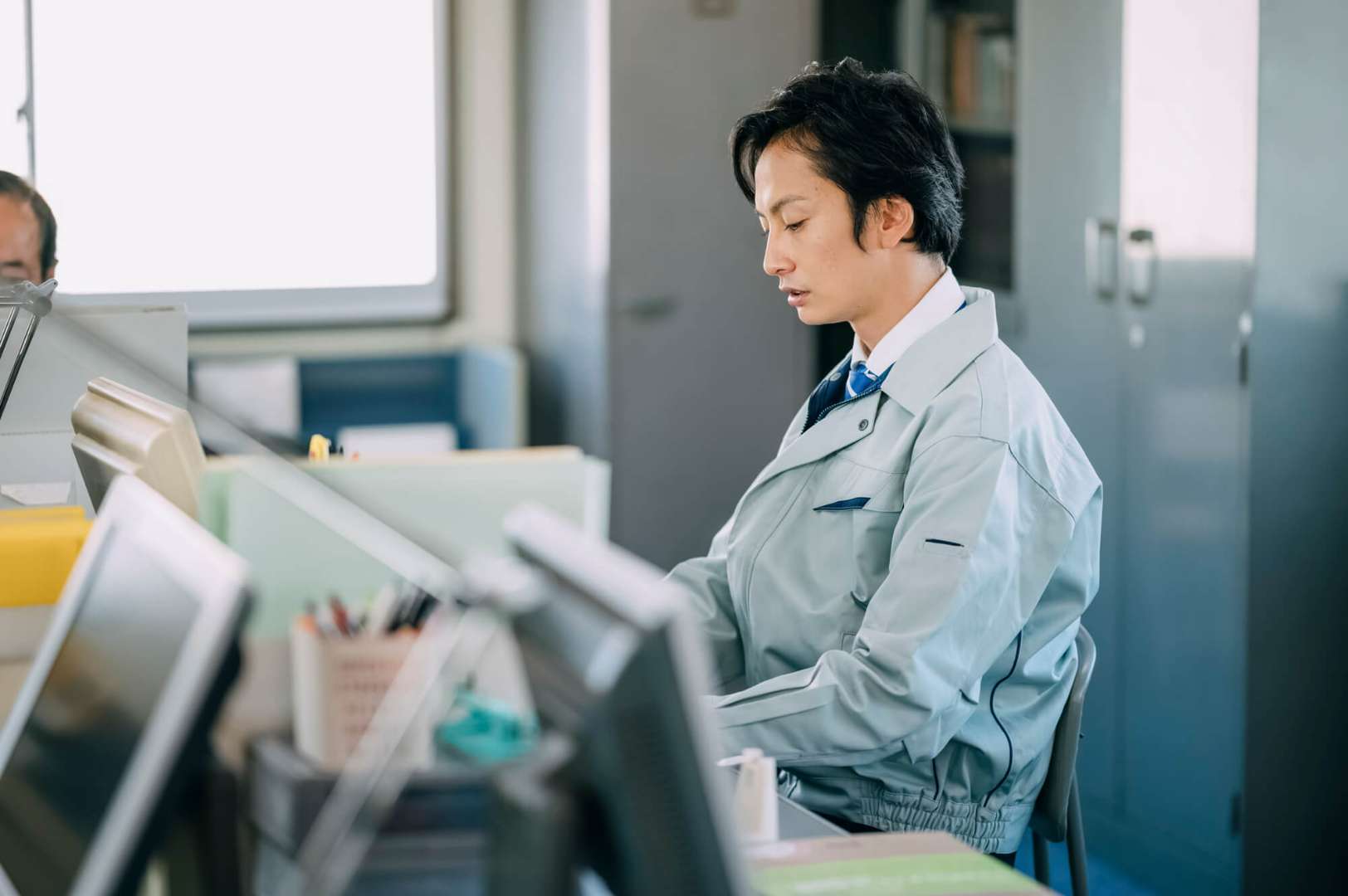
では、なぜ建設業はここまで若者に敬遠され、早期離職に繋がってしまっているのでしょうか。その根本原因は、以下の4つです。
・原因1:根強く残る「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージ
いまだに建設業の代名詞として使われるのが、「きつい・汚い・危険」の「3K」です。工期遵守のプレッシャーから長時間労働が常態化し、全産業平均と比べ休日が少なく有給休暇も取得しづらい「きつい」労働環境は、若者のワークライフバランスを犠牲にしてきた側面があります。加えて、炎天下や極寒といった厳しい屋外環境や、高所作業・重機操作など常に事故のリスクと隣り合わせである「汚い・危険」な作業実態も、若者に敬遠される大きな理由となっています。
・原因2:時代から取り残された古い慣習と文化
「仕事は背中を見て盗め」「長く現場にいる奴が偉い」といった、古い慣習が、業界内に残っている側面があります。
明確な指導マニュアルがなく、先輩の技術を「見て覚える」のが当たり前。上下関係が厳しく、若手の意見が通りにくい年功序列の構造。そして、いまだにFAXでのやり取りや、手書きの紙の日報といったアナログな業務プロセスが主流の会社も少なくありません。
デジタルネイティブ世代である今の若者たちにとって、こうした非効率で旧態依然とした働き方は、時代遅れに映ることは避けられません。
・原因3:経営層と若者の「認識のズレ」
建設業界が抱える課題として、経営層や管理職側と、現場で働く若手との間に、深刻な「認識のズレ」が存在している点も指摘されています。
厚生労働省の調査によると、企業側は、「建設の仕事はきついから辞めるのは仕方ない」「最近の若者は忍耐力がない」と、仕事の厳しさや若者の意識の問題にする傾向があります。
しかし、実際に離職した理由では、「雇用の不安定さ(日給月給制で、休むと給料が減る)」「現場が遠方ばかりで移動負担が大きい」「休みの希望が通らない」といった、待遇面や労働環境、将来への不安を挙げる声が非常に多いという実態があります。このズレを解消しない限り、若者が安心して働ける場所にはなり得ません。
・原因4:労働条件に対する不満
建設業の平均年収は、全産業平均と比較してやや高い傾向にあります。しかし、それは先述したような長時間労働や休日出勤を前提とした数字であることが見受けられました。
貴重なプライベートの時間を削り、心身ともに厳しい労働に従事している対価として、果たしてその給料が十分に見合っているのか。時給換算で考えた場合、決して高いとは言えないケースも多く、その「割に合わなさ」が若者の不満と離職に繋がっていると考えられます。
》施工管理は帰れないって本当?帰れない理由と早く帰るための対策を紹介!
■「当たり前」を覆す建設業界の3つの取り組み

ここまで、建設業界が抱える深刻な課題を解説してきました。
建設業界は、これらの課題を解決し、「若者離れは当たり前」という常識を覆すため、今まさに業界全体で大きな変革に取り組んでいます。
・国が推進する「働き方改革」
業界の古い体質を変えるため、ついに国が本格的に対策に乗り出しており、2024年4月から、建設業にも「時間外労働の上限規制」が適用されました。これは、これまで事実上青天井だった残業時間に法的な上限が設けられたことを意味します。
これは企業にとって、単なる「規制」ではなく、生産性を見直し、効率的な働き方を本気で実現するための「最大の好機」です。 この法改正を追い風に、業界全体で「週休2日制」の普及が急速に進んでいます。公共工事では原則週休2日制が導入され、その流れは民間の工事にも確実に広がっています。「建設業=休めない」は、過去のものとなりつつあります。
・テクノロジーが現場を変える「建設DX」の加速
「建設業=アナログ、体力勝負」というイメージも、もはや過去のものとなりつつあります。今、急速にテクノロジーの導入が進んでいるのです。3Dモデルで設計から施工までを一元管理するBIM/CIMや、ドローン測量、ICT建機が生産性を向上させ、スマートフォンでの図面共有や情報伝達も一般化しました。
こうした「建設DX(デジタルトランスフォーメーション)」の推進は、若手の身体的な負担を大幅に軽減し、長時間労働の是正にも直結しています。特に施工管理のデスクワーク(書類作成や図面修正)などは、デジタル化によって効率化が進み、将来的には一部テレワークやリモートワークを導入する動きも見られます。
・目指すは「新3K(給与・休暇・希望)」への転換
古い「3K」のイメージを払拭すべく、「給与・休暇・希望」を意味する「新3K」の実現を目指す動きが活発化しています。DXによる生産性向上で「給与」を適正化し、働き方改革の遵守で「休暇」を確保。さらに明確なキャリアパスで「希望」を持てる環境整備が進められています。
また、SNSや自社のブログなどを活用し、社会インフラを支える仕事の「やりがい」や「達成感」といった、この仕事のポジティブな魅力を積極的に発信する企業も増加しています。
》建設業の週休2日制は法律で義務化?週休二日が進まない理由と実現への取り組みを徹底解説
》【2025年版】建築・建設業界の今後はどうなる?現状の課題や今後求められる人材を解説!
■後悔しないために!若者が本当に「働きやすい」建設会社の見極め方

業界全体が大きな変革期にあるとはいえ、いまだに古い体質から抜け出せない会社も存在します。
だからこそ、これから建設業界を目指す方々には、「本当に働きやすい会社」を自らの目で見極める力を身につけることが重要です。以下の4つのポイントを、確認してください
・明確な評価制度とキャリアパスがあるか
「給与は経験・能力を考慮」といった曖昧な記載だけでなく、「何をどのレベルで習得すれば、いくら昇給するのか」が分かる給与テーブル(賃金表)やキャリアパスを公開しているかを確認することが重要です。 「頑張れば上がる」ではなく、「何ができれば上がる」かが明確な会社は、評価の透明性が高く、信頼できると言えるでしょう。また、資格取得支援制度(費用の全額補助など)が充実しているかも、社員の成長に本気で投資してくれる会社かどうかの重要な指標となります。
・休みやすさの実績を確認する
求人票の「週休2日制」という言葉には注意が必要です。必ず「完全週休2日制(毎週必ず2日休み)」なのか、「(隔週)週休2日制(月に1〜2回、週休2日がある)」なのかを確認する必要があります。 また、有給休暇の平均取得日数を公開しているか、夏季休暇や年末年始休暇が十分に設定されているかなど、「休みやすさの実績」を具体的に確認することが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となります。
・未経験者を育てる体制とDXへの意欲
「仕事は見て盗め」という会社は、避けるべきでしょう。入社後にどのような研修制度があるのか、先輩社員がマンツーマンで指導する「メンター制度」などが整っているかを確認することが重要です。 また、会社がどのようなITツール(施工管理アプリなど)を導入し、業務効率化に本気で投資しているかを確認してみてください。DXへの意欲は、そのまま社員の負担を減らす意志の表れと言えます。
・会社のリアルな情報を発信しているか
会社の公式ホームページや、SNS、ブログを確認することをおすすめします。 完成した立派な建物の写真だけでなく、そこで働く社員のインタビューや、日々の職場の雰囲気など、「会社のリアルな姿」を積極的に発信しているかどうかが重要です。情報発信に積極的な会社は、透明性が高く、風通しの良い社風である可能性が高いと言えます。
》施工管理にホワイト企業はある?ホワイト企業の特徴や見分けるポイントを紹介!
》建設業の倒産ラッシュから考える、施工管理技士が生き残るための会社選びとは?
■まとめ

建設業の「若者離れ」は、確かに深刻な現実です。それは、「3K」や「古い慣習」といった、業界が長年抱えてきた構造的な課題に起因しています。
しかし、その「当たり前」は今、変わりつつあります。 これは、新しい価値観とスキルを持つ若者にとって、「古い常識を変え、新しい建設業を創る主役になれる」最大の好機でもあります。
ネガティブなイメージだけで判断せず、自らの目で「未来に投資している会社」を見極めることが重要です。この記事が、建設業への理解を深め、キャリア選択の一助となれば幸いです。
■橋本建設は、技術者と会社の未来のために「働き方改革」を推進しています!

・年間休日120日と残業月10時間以下を実現
私たち橋本建設では、社員に心からリフレッシュしてほしいという想いから、2026年から年間休日を120日に設定します。さらに、計画有給5日を加え、実質125日以上の休日を確保する予定です。また、DX化の推進によって残業は月平均10時間以下を達成しており、「19時には帰る」が当たり前の文化です。
たとえば、業務効率化のために施工管理アプリ「ANDPAD」を導入し、現場にいながら書類作成や情報共有を完結させています。また、社内会議も「Zoom」を活用し、会議のための移動時間をゼロにしました。
・「見て学べ」を過去にする研修制度『はしけんアカデミー』
2025年秋には、5年間の成長プログラム『はしけんアカデミー』を開校予定です。ゼロから一流の技術者を目指せる独自の研修制度で、あなたの成長を会社が全力でバックアップします。また、資格手当についても、1級建築施工管理技士の場合は月34,000円など、業界高水準のサポート体制を整えています。
・手厚い住宅・資格手当で、生活と成長をダブルでサポート
私たちは、社員が安心して生活できるよう、月53,000円の住宅手当や月11,000円の昼食補助などを支給しています。もちろん、日々のがんばりは年2回の賞与と業績に応じた決算賞与でしっかりと還元します。
・社員の声が会社を動かす、風通しの良い文化
最近では、女性社員の声から女性専用の更衣室を整備しました。現在、育児休業を取得中の社員も1名在籍しており、ライフステージの変化にも柔軟に対応できる、社長との距離が近い風通しの良い社風が自慢です。
もし、私たちの想いや働き方に少しでも共感していただけましたら、ぜひ一度、ホームページを覗いてみてください。現在、橋本建設ではリフォームの建築施工管理技士や設計プランナーを募集しています。
私たち橋本建設は、創業から60年以上、神戸の街で「人・まち・暮らしの安心を守る」という理念を掲げてきた総合建設会社です。公共工事を中心とした安定した経営基盤のもと、転勤もなく、社員一人ひとりが地域に根ざして長く安心して働ける環境を何よりも大切にしています。
未経験からスタートした20代の若手や、現場で活躍する女性の施工管理スタッフも在籍しており、誰もが安心して成長できる文化がここにはあります。
「まずはカジュアルな雰囲気で話を聞いてみたい」という方も大歓迎です。あなたからのご連絡を、社員一同心よりお待ちしております。
Instagramもやっていますのでぜひご覧ください。
▼関連記事▼
》未経験で施工管理はやめとけって本当?やめとけと言われる理由や働くメリットを紹介!
》施工管理で年収1000万って可能?高年収を目指せる企業の特徴や年収アップのポイントを紹介
》施工管理で「土木と建築」に就職するならどっちがいい?
》「施工管理は意外と楽」と言われる理由は?楽だと思える人の特徴やホワイトな会社の選び方を紹介!
》建設業は「きつい」はもう古い。神戸の橋本建設が働き方改革で目指す、社員第一の未来とは?
代表インタビュー vol.1| 橋本建設が総合建設会社としてメリットに感じていることとは
社員インタビューはこちらをご覧ください
》社員インタビュー|坂本
》社員インタビュー|日下部
》社員インタビュー|市部


