皆さん、こんにちは。神戸市を中心に兵庫県南部で総合建設工事を手掛けている橋本建設株式会社です。
現場で経験を積み、「キャリアアップのためにもう一段上を目指したい」「1級建築施工管理技士の資格を取得して、もっと大規模な工事に携わりたい」。そんな熱い想いを胸に、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。
しかし同時に、「働きながら勉強時間をどう確保すれば…」「合格率を見ると、やっぱり難しそう…」といった現実的な不安がよぎるのも事実です。
さて本日は、そんな想いを持つあなたのために、1級建築施工管理技士について徹底解説します。試験の合格率やリアルな難易度、そしてストレート合格を掴むための学習戦略まで、プロの視点で分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
■一級建築施工管理技士試験の概要

まずは、1級建築施工管理技士がどのような資格なのか、その役割と取得するメリットから見ていきましょう。
・資格の役割とメリット
1級建築施工管理技士は、建設プロジェクト全体を動かす「現場の司令塔」とも言える重要な国家資格です。資格を取得すると、あらゆる建設現場で監督・管理者として、施工計画の策定から工程・品質・安全の管理まで、全ての責任を担うことができます。
特に、法律で設置が義務付けられている「監理技術者」または「主任技術者」として認められる点は、この資格が持つ大きな価値です。大規模で複雑なプロジェクトを率いることができるため、自身のキャリアにおいて大きな武器となります。
さらに、その専門性の高さから、資格取得は年収アップにも直結しやすい傾向にあります。キャリアと収入、両方の向上を目指せる、非常に価値ある資格と言えるでしょう。
・受験資格について
1級建築施工管理技士の試験は「第一次検定」と「第二次検定」に分かれており、それぞれ受験資格が異なります。
第一次検定: 試験実施年度に満19歳以上であれば、学歴や実務経験を問わず誰でも受験可能です。
第二次検定: 第一次検定合格後、学歴に応じた一定期間の実務経験が必要となります。
制度が少し複雑で、現在は経過措置期間でもあります。これから受験を考えている方は、必ず「建設業振興基金」の公式サイトで最新の受験資格を確認するようにしましょう。
・筆記試験と実地試験の違い
第一次検定と第二次検定では、問われる能力が異なります。
第一次検定(マークシート形式): 建築学や法規、施工管理法など、幅広い分野の知識が問われます。この検定に合格すると「1級建築施工管理技士補」の資格が得られます。
第二次検定(記述・マークシート形式): 第一次検定で問われた知識を、実際の現場でどう活かすかという実践的な応用能力が問われます。特に、自身の工事経験を基に記述する「経験記述」は、合否を分ける重要なポイントです。
》【2024年最新】建築施工管理技士の受験資格緩和で何が変わる?変更点や注意すべきポイントをわかりやすく解説
》1級建築施工管理技士はいきなり受験可能?受験資格と最短の合格ルートを徹底解説
■一級建築施工管理技士試験の合格率
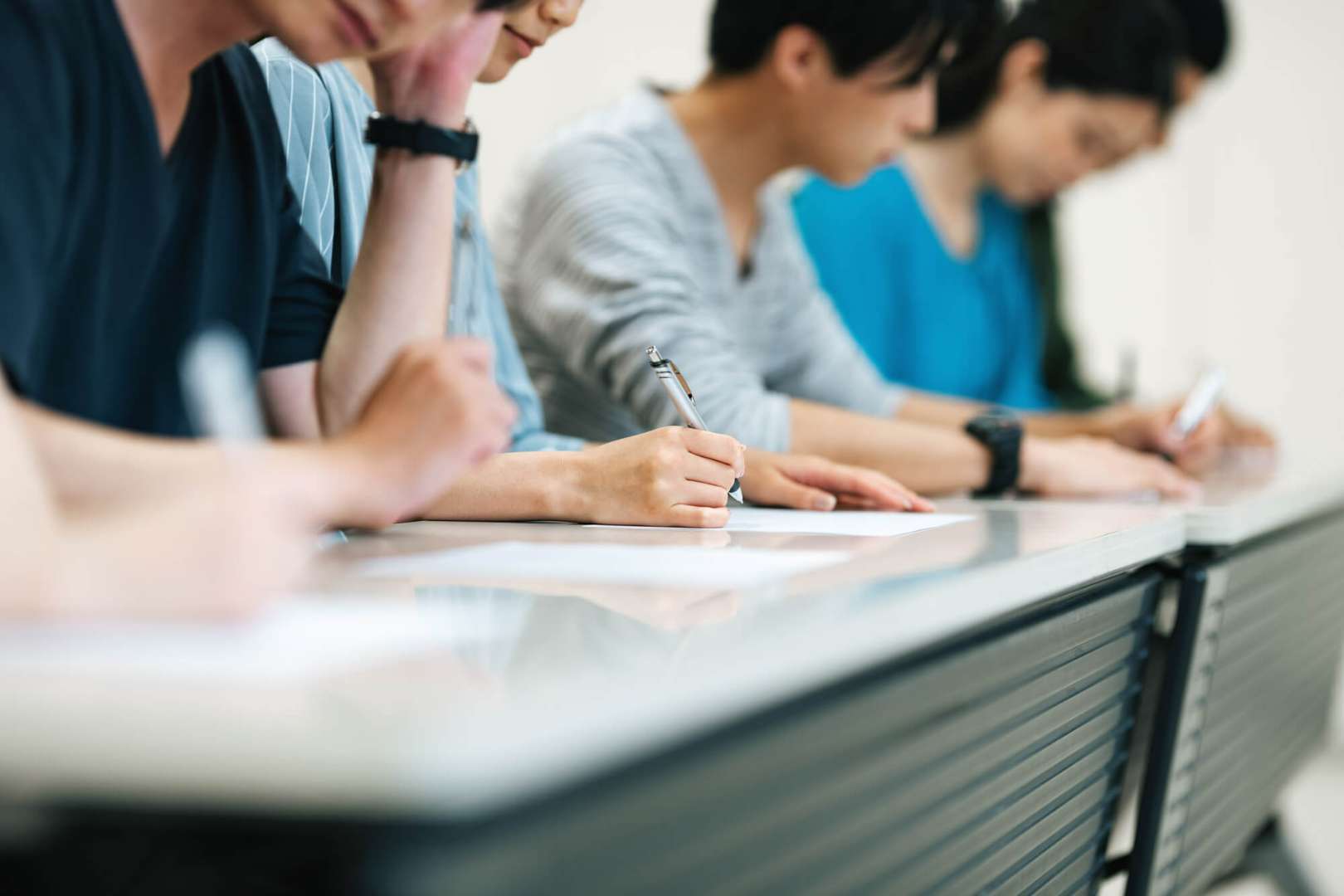
次に、試験の合格率と、実際の難易度について見ていきましょう。
▼第一次検定の合格率
2024年度 36.2%
2023年度 41.6%
2022年度 46.8%
2021年度 36.0%
2020年度 51.1%
2019年度 42.7%
2018年度 36.6%
▼第二次検定の合格率
2024年度 40.8%
2023年度 45.5%
2022年度 45.2%
2021年度 52.4%
2020年度 40.7%
2019年度 46.5%
2018年度 37.1%
※一般財団法人建設業振興基金の施工管理技術検定の公表データより
第一次検定の合格率は40%前後、第二次検定は45%前後で推移しています。この数字だけ見ると「半分近くが合格するなら、意外と難しくない?」と感じるかもしれません。
しかし、同年度内に第一次・第二次の両方に合格する割合は10%台とも言われ、決して簡単な試験ではないことがわかります。
■ 一級建築施工管理技士の難易度

一級建築施工管理技士試験の難易度がどうなっているか、具体的に確認してみましょう。
・試験の合格基準
一級建築施工管理技士試験では、第一次検定、第二次検定ともに得点率が60%以上で、合格となります。
これは裏を返せば、満点を取る必要はないということです。試験範囲のすべてを完璧にマスターしようとするのではなく、基本的な問題を確実に見極め、得点を積み重ねていく戦略が非常に重要になります。
ただし、第一次検定では全体の得点率が60%以上でも、「施工管理法(応用能力)」の分野で得点率が60%を下回ると、いわゆる「足切り」となり不合格になってしまうため注意が必要です。
・合格率に影響を与える要因
一級建築施工管理技士試験の合格率に影響を与える要因は、単に問題が難しいというだけではありません。いくつかの複合的な要因が絡み合っています。
第一に、試験範囲が非常に広大であることが挙げられます。建築学の基礎、各種工事の施工技術、品質・安全管理、そして建設業法や労働安全衛生法などの関連法規まで、学習すべき項目は膨大です。これらすべてを網羅的に理解し、記憶しなければなりません。
次に、2021年度の制度改定で試験内容が変更された点も挙げられます。特に第二次検定で出題される「経験記述」は、本試験における最大の難関と言えるでしょう。なぜなら、経験記述では単に工事内容を報告するのではなく、現場で直面した課題をいかにして乗り越えたかという、課題解決能力や応用力、そしてそれらを論理的に記述する文章構成力が厳しく問われるからです。参考書の丸暗記では、決して太刀打ちできません。
さらに、受験者の大半が、現場の第一線で働く社会人であるという点も見逃せない要因です。日々の多忙な業務や不規則な勤務の中で、学習時間を安定して確保すること自体が難しく、これが合格への現実的なハードルを高くしています。
■ストレートで合格するための学習方法と対策

では、この難関を突破し、ストレート合格を掴むためにはどうすれば良いのでしょうか。日々の業務で忙しい社会人でも実践できる、3つの学習戦略をご紹介します。
・余裕を持ったスケジュールで勉強する
現場の仕事は多忙で、急なトラブル対応などもあり、計画通りに学習時間を確保するのは難しいものです。だからこそ、最低でも試験の半年前、可能なら一年前には勉強をスタートさせ、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
「今日は疲れたから明日やろう」という一夜漬けの学習では、知識の応用力が問われるこの試験には太刀打ちできません。毎日の通勤時間や寝る前の30分など、スキマ時間を有効活用し、コツコツと知識を積み重ねていきましょう。
・制度改正後の問題の傾向を知っておく
2021年度に試験制度が改定されて以降も、出題傾向には少しずつ変化が見られます。過去問を解くことはもちろん重要ですが、必ず最新年度の過去問から遡るようにし、現在の出題形式や頻出分野を把握しましょう。
市販のテキストやオンライン講座などを活用し、制度改定後の問題傾向を掴んだ上で学習を進めることが、合格への最短ルートです。
・経験記述の対策を念入りにする
一級建築施工管理技士試験で特に難易度が高いとされているのが第二次検定の経験記述の問題です。配点も高く、ここで躓くと、合格が難しくなります。
経験記述では、これまでに経験した工事の内容を思い出して記述する部分があります。もし詳細を忘れていると、回答を書くことさえできなくなってしまうのです。
細かな内容も問われるので、ウソの記述をしてごまかすことはできません。また、参考書の丸写しも通用しません。
では、どのように対策をすればいいのかというと、対策の鍵は「事前準備」です。
・これまでに携わった工事をリストアップする
・それぞれの工事で、安全管理・品質管理・工程管理などにおいて「工夫した点」「苦労した点」「改善した点」を具体的に書き出す
・出題傾向を分析し、想定されるテーマに合わせて、上記の経験を文章化する練習を繰り返す
自身の経験を事前に整理し、「このテーマならこの経験を書く」と決めておくだけで、本番での対応力は格段に上がります。日頃から、工事が終わるたびに工夫した点をメモしておく習慣をつけるのも非常に効果的です。
■まとめ

今回は、1級建築施工管理技士試験のリアルな難易度と、合格を掴むための戦略について解説しました。
合格率は決して高くなく、難易度の高い試験であることは間違いありません。しかし、それは裏を返せば、計画的に正しい努力を継続すれば、必ず合格圏内に入れるということでもあります。この記事が、あなたの挑戦への第一歩を後押しできれば幸いです。
■橋本建設ではリフォームや公共工事の建築施工管理技士を募集しています!

現在、橋本建設ではリフォームや公共工事の建築施工管理技士を募集しています!
そこで、橋本建設の特徴をご紹介しましょう。
まず、弊社は神戸市で公共工事や民間の建築工事、住宅リフォームなどを行う総合建設会社(ゼネコン)です。創業50年で、長年の実績を基に安定かつ確実な工事を行っています。その実績が認められ、神戸市優良工事表彰を2年連続受賞しました。
弊社には、未経験から入社したスタッフや女性の施工管理スタッフも在籍しています。未経験で大丈夫かなと不安にもなるでしょうが、指導は丁寧に行うのでご安心ください。
20・30代の先輩社員も在籍し、若い方や新卒・未経験の方もともに協力しながら歩んでいけます。
弊社は神戸市を拠点に地域密着のため、転勤もなく、働きやすい環境を整えています。
年間休日は113日にアップ。ゆくゆくは120日目標で考えています。また有給取得推進日を設けており、(時間単位での取得も可能)、積極的に有給を消化できます。
資格取得支援制度や資格手当などの福利厚生も充実。働き方改革に向けたDX導入も推進しております。
当社の社員インタビューはこちらをご覧ください
》社員インタビュー|橋本建設株式会社
最近では、働きやすい環境を整備のため、本社ビルのリニューアルを行い、トイレや更衣室の改修なども行いました。
》本社ビル リニューアルのお知らせ
Instagramもやっていますのでぜひご覧ください。
そんな橋本建設で一緒に働きませんか。皆さんの応募をお待ちしております。
▼関連記事▼
》一級建築施工管理技士がすごいと言われる理由とは?取得のメリットや転職に役立つ理由を紹介
》1級建築施工管理技士になると年収はどうなる?2級との違いや転職事情も紹介!
》施工管理の転職でおすすめのタイミングは?転職を成功させるために知っておくべきポイントを紹介!
》施工管理にホワイト企業はある?ホワイト企業の特徴や見分けるポイントを紹介!
》建築施工管理におすすめの転職先は?選ぶ際のポイントや注意点を解説
代表インタビュー vol.1| 橋本建設が総合建設会社としてメリットに感じていることとは


